我が子がぜんぜん集団行動ができない…
集団行動ができないということは発達障害なの?
どうしたらできるようになるの?
こんなお悩みをお持ちの親御さんもいるのではないでしょうか。
集団行動ができないと、学校や幼稚園で子どもが困ってしまうのでは……と、親御さんとしては心配ですよね。
また子どもが集団行動ができないと、学習障害や発達障害などを心配する親御さんもいると思います。
もちろん発達障害が集団行動に及ぼす影響は大きいですが、必ずしもこれらだけが問題ではない場合があります。
今回は集団行動が苦手な理由やその対処法などについて書いていきます。
【集団行動が苦手・できない理由】
集団行動ができる年齢に達していない
一般的に集団行動は2歳から3歳くらいまではまだ難しく、6歳くらいからできるようになります。
ですから、子どもの年齢を見て、早すぎる時期から集団行動ができるようになると期待するのは止めておきましょう。
6歳くらいまでは、集団行動であってもミスがありますし、大人は広い心で見守ることが大切です。
というのも、ミスを叱るといった行動を親御さんがしてしまうと、集団行動に自信が持てず、より一層できなくなることも多々あるからです。
もちろん集団行動ができる発達年齢まで待つことも大切です。
しかし個人差によっても集団行動ができる、できないは変わってくるので、決して焦らず叱ることがないようにしてください。
個人の性格や性質
集団生活になじめるかどうかは、子どもの性格や性質、個性によっても大きく変わり、それによって得意・不得意があります。
《集団生活が苦手と思われる子どもの性格》
大人しく内向的な性格・引っ込み思案
自己中心的で目立ちたがり屋
マイペースでおっとりしている
多くの場合は、声かけやサポートで自分なりの集団生活での馴染み方や他人との距離の取り方、接し方を取得していけるでしょう。
一方、馴染めているように見えても本人が無理をしている場合もあります。
そのような場合も適切なサポートをしていけるといいですね。
学校生活など集団行動で疲れてしまっても、自宅や休日に自分らしくいられれば、また月曜日からがんばって行ける子も少なくありません。家庭と学校での生活のメリハリをつけてあげるのも1つの方法です。
発達障害やグレーゾーン
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動性症)、またはLD(学習障害)などの発達障害、または診断がつかなくてもグレーゾーンの特性があり、社会性やコミュニケーションに難があって不安や困り感につながっている子もいます。

自分でも「なんで友達と同じような行動が取れないのかわからない」「衝動性が強く我慢できない」そういった特性を持つ子もいるのです。
他にも、指示が理解しにくい、興味や関心に偏りがある子なども集団行動を難しく感じるでしょう。
療育や特別支援学級などでの対応で、徐々に集団行動に慣れていくこともできます。
しかし発達障害の度合いにもよるので一概にどれくらいできるようになるのかは分かりません。
発達障害を抱えている可能性があるかもしれないと思ったら、専門家に相談してみるのが一番です。
集団行動が取れないだけではなく、そのことでその子が生きづらさを感じている可能性もあります。
少しでも心配に思ったら、1人で悩んだりせず専門家の判断を仰ぐのが一番です。
発達障害の子を専門的に見ている先生から、適切なサポートの仕方が得られることがあるので、不安に思ったら早めに相談してみましょう。
環境や状況が要因になっている
集団行動が苦手な子どものなかには、環境や状況に原因がある子もいます。
例えば、同じ学年の子と接する機会が少なかった、一人っ子や転勤が続いたなど、今まで集団行動をしてこなかった子が急にできるようになるのは難しいですよね。
社会性や協調性を培う体験や機会不足が原因で、うまく行動できないことも十分に考えられます。
原因の一つとして、コロナ禍で外出が減り、他人とのコミュニケーションが足りていない場合もあります。
また、吃音・ケガや障害をからかわれたなどのことがきっかけで他者と距離を取っているなんてことも。
本人から集団行動をしない理由を聞く、もしくは観察するなどして集団行動の機会を増やしていくことが改善につながることもあります。
【集団行動ができるようになるのは何歳ごろから?】
3歳までの子ども
3歳までは他人の気持ちをなかなか考えられず、1人あそびがほとんどで他人の気持ちを想像できない子が多いでしょう。
3歳くらいまでは、集団生活での集団行動を意識するのはまだ難しく、同じ場所であそんでいても、互いに関わり合いを持たない「平行あそび」がほとんどです。
まずは、おもちゃの取り合いから貸し借りを学び、遊具の順番待ちや譲り合いなどを通して、他者とのコミュニケーションを学びましょう。
その後、何回も何回も複数の子たちとあそぶことで、他者の存在に気付き始め、集団生活や集団行動を少しずつ意識するようになります。

4~5歳の子ども
4、5歳になるとやっと友だちとあそび始めるようになります。
まずは、1人から2人、3人とあそび仲間が増えていくことで、仲間がいることの喜びや楽しさを学び始めるのが、幼稚園や保育園の年中・年長の頃です。
ただし、みんながこの時期に仲良くあそべるわけではありません。
自己中心的な子も多くケンカも増えますが、そこで他者ともめることで我慢や譲ることも覚えていく時期です。
対人関係が苦手な場合は、ここで「衝突を避ける」「相手に譲る」「声をかける」「謝る」など自分なりの対応や処世術などをじっくり学ぶ機会となります。
もちろん大人の援助は必要です。


6~7歳の子ども
小学校に入って、運動会や文化祭、遠足などのイベントで友達と何かを成し遂げる喜びや達成感をやっと感じられるようになります。
ただ、保育園や幼稚園で何を体験してきたかという経験が大きく影響するのも事実です。
人数の少ない保育園や自宅保育だった子の場合はまだ少し時間がかかるかもしれません。
さまざまな体験から徐々に身につくものなので、小学校低学年くらいのときは、集団行動に苦手意識があっても当然です。
しかし、小学校生活では集団行動が必須なので、苦手意識が高いと対応が難しく困ることになるかもしれません。
集団生活が苦手な様子があれば、就学前後によく先生とも相談して対応を検討するようお願いしましょう。
【集団行動が苦手な子どもの対処法】
それでは、集団行動が苦手な子どもにはどのように対処していったらよいのでしょうか?
叱らずに、言葉かけをし、じっくり話をする
自分勝手な行動をしてしまう性格のせいで集団行動が苦手な場合、集団行動が必要な理由を明確に、さらに具体的に説明することが大切です。
周りから見ると自分勝手な行動に見えるかもしれませんが、実は集団行動の必要性をわかっていないだけかもしれません。
なぜ今みんなと同じことをしないといけないのか理解できず、常に自分のペースで動いてしまう子もいます。
ほかにも、やりたいことをやりたい時にしてしまうのは、ただマイペースな性格だからなのかもしれません。
集中力がありすぎて、好きなことに没頭し、周りが見えなくなってしまう子もいます。
そのような子たちには、頭ごなしに叱りつけても逆効果です。
今なんで自分の好きなことをしてはいけないのか、自分の行動が、ほかの子の邪魔や迷惑になる理由や状況を根気よく説明するといいでしょう。
不安な気持ちを取り除く
集団行動が苦手な子どものなかには、緊張や不安が原因でうまく集団に入れない子もいます。
例えば、引っ込み思案で大人しい子や不安を感じやすい子は、集団に慣れるまで時間がかかります。
慎重すぎる性格や、行動やおしゃべりが早くできない子もそうです。
その場合は、親や信用できる教師がそばについて予行演習をするのも有効です。
集団行動には体験の積み重ねも必要なので、機会を増やし、繰り返し行って自信をつけさせてあげると安心できるようになります。
また「参加せず、どのようなことをしているのか見ておく」というのも、不安を取り除くのに有効です。「一緒にしなくていいの?」と思われるかもしれませんが、「見る」ことも立派な参加方法です。
時間はかかっても、見ることで自分なりの参加方法が分かってきます。
場数を踏む・予行演習をする
何をすればいいかは分かっているけど、失敗が怖くてできないといった子どももいます。
この状況は親御さんとの予行演習がピッタリです。
やはり集団行動には体験が必要なので、繰り返しおこなって自信をつけさせることが効果的です。
上記でも述べたような「見る」ことも有効な方法です。
指示が理解できない場合
未就学児や小学校低学年の子どもは、聞いているようで意外と理解できていないことが多いものです。
指示が理解できていないので、なにが分からないのか、言葉にできずにいる場合もあります。
まずは、大人が簡単な指示を出し理解できているかどうかを確認してみましょう。
学校の先生は生徒たちみんなに話しかけているつもりでも、その子は「自分以外の誰かに話しかけている」と認識しているのかもしれません。
先生の話がわからなかったり、聞いていなかったりするせいで集団行動が苦手な場合があるので「先生がなんて注意してたかわかる?」と確認してみるといいでしょう。
先生が言ったことを復唱させ、言い換え表現ができるか確認すると理解の程度がわかります。
もし、子どもが理解できない場合は先生に質問できるようにすることや、もう一度言ってもらえるようにすることなどを伝えましょう。
先生にも保護者面談などで「聞いているように見えるけど理解ができていない」「自分事にならず、理解が乏しい」など伝え、サポートをお願いすると安心です。
【集団行動が苦手なちょっと気になる子】
子どもの育ちは子どもそれぞれなので、お子さんの発達状況について不安を感じる保護者の方もいるのではないでしょうか。
子どもが今どのような状態なのかを確認しつつ、子どもの現状にあったサポートをするのが大切です。
しかしもともと集団行動が苦手という特性をもった子どももいます。いわゆる発達グレーゾーンの子どもや発達障害の子どもです。
生まれつきの脳の働き方の違いで行動面や情緒面に特徴がでるため、保護者が育児の悩みを抱えやすくなります。
また、子ども自身が生きづらさを感じることもあります。
発達障害には自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などがあります。
ここではそれぞれの特徴をかんたんに説明します。
発達障害の特徴
自閉スペクトラム症
・コミュニケーションがうまくとれない
・対人関係が苦手
・こだわりが強い
という特性をもちます。
遊びの場面では、車を一列に並べ続ける、タイヤの動きを眺める、ルールを理解して友だちと遊んだり空気を読むことが苦手、という姿が見られます。
他には、「バイバイ」をするときに手の平を自分にむける、視線が合いにくい、共同注視が難しい、ことばの発達の遅れなどが特徴として挙げられます。
注意欠如・多動症
発達年齢に比べて
・落ち着きがない
・集中力がない
・衝動的
という特性があり、症状の現れ方によって特徴が異なります。
落ち着きがない子はお部屋をウロウロ歩き回り、決まった時間や場所での行動ができない、衝動的な子は感情のコントロールが苦手で、コミュニケーションミスから友だちとトラブルになりやすい、などそれぞれ特徴はありますが、どの症状が現れても叱られることが多くなりがちなため適切な支援が必要です。
LD
LDは学習障害全般を指す言葉です。
学習障害には次のような種類にわかれ、指示が理解しにくい学習障害だと集団行動が苦手になります。
● 読字障害
● 書字障害
● 算数障害

これら3つはわかれており、LDとADHDが合併することもあります。
しかも局所的な学習障害もあり、算数に問題はないけれど、指示をうまく理解できないといったようなこともあります。
そのため、発見が遅れてしまうこともあるので、親御さんはお子さんの行動をよく観察してあげてください。
仮に学習障害が疑わしいとなっても、さまざまなテストを行わないと発見できない障害です。
気になる場合は迷わず相談を
発達障害の子どものサポートは早い時期から始める方が良いといわれています。
子どもの発達が気になる場合、まずは市の健診で相談してみてください。
お住まいの地域によって異なりますが、医療と福祉の連携があり支援体制が整っている場合があります。
医療機関に直接相談する場合は、小児科、児童精神科、小児神経科、または発達外来のある病院になります。
大学病院や総合病院への受診はかかりつけ医の紹介状が必要な場合がありますので受診前に確認してくださいね。
悩んだり、困ったりした際は、一人で抱え込まず専門家に相談しましょう。
【まとめ】
集団行動は大人が思っている以上に難しいものです。
成長や発達、個人の性格やその子が育った環境など、たくさんの要因があって苦手だと感じる子がたくさんいます。
集団行動が苦手な場合は、適切な発達年齢までまずは待つこと、適切な時期に集団行動の機会を増やして必要性や協調性を学ぶことが大切です。
慣れることで徐々に身につくことも多いので、叱るのではなく集団行動の必要性を説明し、サポートすることが大切です。
不安なことや分からないことがあれば、学校の先生に相談しながら子どもたちに寄り添ったサポートができればいいですね。

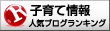
コメント