人前で話すことが苦手な子もいます。
大勢の前で発表させようとすると、恥ずかしがったり嫌がったりもじもじしたりして、話すことに自信のない子どもです。
そのような子には
- 無理強いをしない
- 話しやすい雰囲気を工夫する
- 答えやすい質問にする
- ジェスチャーで表現する
など話しやすくする工夫をしてあげましょう。
しかしいろいろな手立てを講じても、話すことが求められる場面や状況で話すことができなくなるケースは、緘黙症(かんもくしょう)が疑われる場合もあります。
それでは今回は緘黙症についてまとめてみたいと思います。
【緘黙(かんもく)とはどのような症状か?】
緘黙症には「全緘黙症」と「場面緘黙症」の2つがあります。
全緘黙症と場面緘黙症
全緘黙症はどのような場面でも話をすることができなくなっている場合です。
一方、場面緘黙症は特定の場面で話をすることができなくなってしまう場合です。
一般的に場面緘黙症の子どもは、話をしたくなくて話さないのではなく、話をしたくても話すことができない状態なのです。
緘黙症の症状や状態
場面緘黙症は、5歳前後で発症することが多く、話す機会が増える小学校へ行くまで顕在化しないことも多いようです。
特に幼児のころは、友だちとあそんでいる時は普通に話ができる、慣れた大人とは小声で話をするなど、話ができているケースがあるために、場面緘黙症の理解や支援が受けにくいということもあります。
【関わり方のポイント】
緘黙のある子どもに対する大人の誤解が状態を悪化させることもあります。
以下のよくある誤解について理解して、正しい対応を心がけましょう。
緘黙の誤解と対応
❌おとなしい性格であるだけで、放っておいてもそのうちしゃべるようになるだろう。
⇒⭕早い時期からの専門家の支援や話すことが楽しいと思える体験が必要です。
❌家庭で甘やかせすぎて過保護なだけではないか。
⇒⭕古い考えに基づいた誤解です。専門家の支援や話すことが楽しいと思える体験をさせてみましょう。
❌年齢に見合ったしつけができていないだけではないか。
⇒⭕あいさつや返事、人前で話をしないのは人を無視しているからではありません。
❌わざと黙っているのではないか。
⇒⭕反抗的だと誤解されがちですが、困っている表情がうまく表現できないのかもしれません。
❌孤立は自分のせいであって、自分から積極的に友だちの輪の中に入るよう努力するべきではないか。
⇒⭕友達の輪に入ると集団のテンポに合わせたコミュニケーションが必要になります。タイミングの良いコミュニケーションスキルを獲得することは、その子だけの努力では改善が難しい場合があります。
❌1人でいても平気そうだから放っておいてよいのではないか。
⇒⭕緘黙のある子は、表情に不安が表れないこともよくあります。決して1人で平気という訳ではありません。
❌緘黙は内気な性格の子どもしかおらず、気の強い子どもは緘黙ではない。
⇒⭕性格は様々です。内気か気が強いかというだけでは判断できません。
❌話をするように子どもに指導するべきではないか。
⇒⭕発話や返事をさせることばかりに注目しないことが大切です。過度なプレッシャーは症状を悪化させます。
❌「うなずくだけ」など意思表示のためのジェスチャーを許していたら甘やかすことになるのではないか。
⇒⭕非言語的なコミュニケーションを十分行うことが、発話や対話へとステップを進めます。しかし、場合によっては専門家に相談しましょう。
大人ができる対応
大人ができる子どもへのサポートは、不安のない環境を整えること、子どもの自信を育てること、他人(友だち)と楽しく交流ができる機会を用意することです。
緘黙の症状で親が気になった場合は早めに療育センターなどの専門機関に相談しましょう。
緘黙は「親の育て方のせい」と気に病む必要はありませんが、子どもへの理解と接し方の工夫が必要になる場合があります。
園や集団の場面では、子どもは緊張や不安を抱えている場合が多くあります。
家庭では体を使ったあそびや活動、家族との会話やお手伝いなどを通して、自分に自信が持てることを増やしてあげましょう。
また、友だちとの交流は、親が過剰にならない程度にサポートしましょう。
不安への対応力を育てるために、感情をコントロールしたり、適切な自己表現をしたり、他の解決方法を考えたりする経験ができるように、家庭内で少しずつチャレンジの機会を持つといいですね。
【緘黙症になりやすい要因】
場面緘黙の原因やメカニズムについては、まだはっきりとはわかっていません。
単一の原因によるものではなく、本人がもともと持っている不安になりやすい気質に加えて、心理学的要因や社会・文化的要因など、複数の要素が影響しているのではないかと考えられています。
また、過去には場面緘黙のすべてがトラウマに関連づけられていたこともありますが、現在ではほとんどの子どもに関係しないことがわかっています。
一方でショックな出来事の後に急激に話ができなくなったり(トラウマ性緘黙)、身体的虐待や精神的虐待がある場合、場面緘黙や場面緘黙に似た状態を示すこともあり、それぞれ分けて支援について考える必要があると言われています。
【まとめ】
緘黙の子どもの割合は約0.2%。500人に1人という報告があります。
無理に治そうとするのは逆効果。
緘黙の子どもにとっては周りの環境を整えてあげることがとても大切です。
そして気になるときは専門機関に相談を。
緘黙を持つ子どもにとって過ごしやすい環境を作ってあげたいですね。

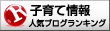


コメント