女の子と男の子だと育て方で共通するところもありますが、全く違ってくるところも多いと思います。
特に女の子は大きくなればなるほど、接し方も難しくなっていくのではないでしょうか。
そこで今回は、教育カウンセラーの諸富祥彦の著書「女の子の育て方」を読んで、女の子を幸せに育てる方法についてまとめてみたいと思います。
【お母さんが幸せなら女の子も幸せ】
教育カウンセラーの諸富祥彦さんによると、女の子の子育てにおいて「基本の基本」「大原則」となるものは
「お母さん自身が幸せでいること。それが幸せな女の子を育てる大原則」
ということだそうです。
それはなぜかというと、
女の子は同性であるお母さんの影響をダイレクトに受けます。お母さんが娘さんの人生のモデルそのものになるからです。
お母さんが毎日楽しそうに過ごしていれば、娘さんは必ず、
「人生って楽しいものなんだ」と感じて、生きることに積極的になります。
とにかく大切なことは「お母さん自身が、心から幸せになって生きていること」なんです。
働きにも出ず、つきっきりで子育てをしなくてもいいんです。
仕事を辞め、趣味もあきらめ、育児に専念…そうでなくてもいいんです。
もしお母さんが、自分のやりたい仕事や趣味を押し殺して、義務感と責任感から子育てをしていれば、その不満な気持ちは必ずお子さんに伝わってしまいます。
お母さんが仕事をしていて、子どもを保育園に預け、毎日4時間くらいしか一緒にいられなくても、その4時間に、お母さん自身が幸せいっぱいでいられるならそれでいいんです。
その幸せな気持ちがお子さんに伝わって「お母さん、私といるとうれしいんだな。幸せなんだな」と感じてくれるはずです。
お母さんは幸せであること。それがお子さんを幸せな女の子にする一番の近道といえるのです。
☆↑↑↑GOM Mixはこんな方におすすめ!☆
- 動画編集・YouTuberを始めたい動画編集初心者の方
- ロゴ出力や機能制限など完全無料ソフトウェアを使いたい
- これまで動画編集の難しさに直面していた方
- 簡単に使えて動画編集を楽しいたい方
- 手軽に動画編集を行いたい(結婚式ムービーやお子さんの思い出動画作りに大活躍!)
- 写真を複数つなげて動画を作成したい方
- 動画編集の副業を始めたい方
【子育ての3つのステージ】
「女の子だからって、甘やかしすぎるのはよくない」
「早い内から、しっかりしつけた方がいいはず」
そう思ってしまう方も少なくないと思います。
でもそれは違うんです。
小学校に入るくらいまでは、思いっきり親バカになって「これでもか!」というほど溺愛するのが一番です。
「早い内からしつけを」と思って、厳しく叱り続けてしまうと「お母さんは私のことが嫌いなんだ」「お母さんは、私なんてダメな人間だとおもっているんだ」という気持ちを持ってしまいます。
とはいっても、いつまでも溺愛していればいいわけでもありません。
お子さんの成長に応じて、子育ての仕方も変えていく必要があるのです。
具体的には次の3つのステージとして目安があります。
①ラブラブ期(0~6歳くらいまでの乳幼児期)
②しつけ期(6歳~12歳くらいまでの児童期)
③見守り期(12歳~18歳くらいまでの思春期)
①のラブラブ期は、子育ての土台ともいえる重要な時期です。お子さんに「あなたのこと大好き!」とたくさん愛情を注いであげて下さい。
そんな子どもは「お母さんからこんなにも愛されている。私ってかけがえのない存在なんだ」と感じられるようになります。
すると子どもの心に安定感が生まれ、「私は大丈夫!」「いろいろなことにチャレンジしてみよう!」という自信=自己肯定感を持てるようになります。
この自己肯定感を育てるためには、お子さんに惜しみない愛情を注ぐことです。
そのためには「タッチング」と「ポジティブな言葉がけ」で思い切り愛情を伝えてあげて下さい。
具体的には
・心を込めてゆっくり抱っこする
・ペタペタさわる
・ギュッと抱きしめる
・ほっぺにキスをする
などです。
また「○○ちゃんかわいいね」「○○ちゃんのこと、すごく大切だよ」と言葉に出して伝えてあげて欲しいのです。
言葉に出して具体的に愛を伝えることは、女の子にとって大きな拠り所になります。
ストレートな言葉で愛情をどんどん口に出していきましょう。
【しつけには「我が家ルール」を】
②のしつけ期(6~12歳)は、基本的には①のラブラブ期の延長と考えていいと思います。
まだまだ小学校低学年くらいまでは、どの子もまだ甘えん坊です。
お子さんを溺愛してあげて下さい。
ただ、しつけ期ですから、しつけもしっかり行っていくべき時期です。
学校で社会のルールも教えてくれますが、なにもかも学校任せにせず、「世の中のルール」「やるべきこと」「やってはいけないこと」は、しっかり教えてあげましょう。
女の子のしつけのポイントは次の3つです。
①「ダメ」や「ノー」を言葉にして伝える
②子どもの自発的な行動や判断を尊重する
③最低限守るべき「我が家のルール」を決める
①「ダメ」や「ノー」を言葉にして伝える
子どもが「泣いて騒げば、何でも思い通りになる」という接し方は良くないです。
ダメなものはダメとしっかり伝えないといけません。
しかし感情的に叱ったり、頭ごなしにダメを押し付けるのはNG。

具体的にどのような言い方がいいのか…
⭕️「ここで騒がれると他のお客さんの迷惑になるなぁ。あなたならきっとできるはずだから、もうちょっと静かな声で話してくれたら、お母さんうれしいな」
❌「こんな場所で騒いで(あなたは)なんて悪い子なの!(あなたは)どうして言うこと聞けないの!」
「自分(お母さん)」を主語にして自分の気持ちを伝えるのがいいですね。
「あなた(子ども)」を主語にして、子どもを責めてしまうと「お母さんは私のこと嫌いなんだ…」と自分に否定的な気持ちを持ってしまいます。
②子どもの自発的な行動や判断を尊重する
子どもには「あれしたい」「こうしてみたい」という考えがあります。
そう思ったことや考えたことを、積極的に行動に移してみようとするのです。
親からすれば「時間がかかる」「うまくできっこない」と感じることがあるかもしれませんが、その行動を否定せず、ドンと構えて、根気強くサポートしてあげて下さい。
でも「失敗させたくない」「きちんとやらせてあげたい」という思いから、手出し・口出しをしてしまいがちですが、ここはグッと我慢して、見守り、サポートに徹してあげましょう。
お膳立てをしてしまうと、子どもの自立心を奪ってしまいます。
③最低限守るべき「我が家のルール」を決める
小学生の女の子は、親の行動や反応をよく観察し、それをモデルにしながら、いいこと悪いことなどを自分なりに学んでいきます。
小学生の時期は、社会のルールやマナーを育てていくのに最適な時期です。ただしあまりに細かく注意しすぎるのではなく、「これだけはしてはいけない」という最低限の『ルール』を決めて、子どもが自分で守れるように促していきましょう。



「我が家のルール」の一例をあげておきます
「よそのお家に行ったら、挨拶は忘れずにしようね」
「暗くなる前に、必ずお家に帰ること」
「お友だち同士でのお金の貸し借りは絶対ダメ」
「お友だちを傷つける言葉(死ね・殺す・ウザいなど)は絶対言ったらダメ」
こういったルールをきちんと身につけさせることが、お子さんの心や体を守る大事な「枠」となるということです。
\当サイトで使用しているテーマです/

書きやすい!初心者でもデザイン性抜群のサイトに
一番おすすめのWordPressテーマ「SWELL」
【思春期には家にいてあげるといい】
10歳くらいになり思春期に入ると、子どもは自分の考えを持つようになります。
親からの指図などをうっとうしく思い始め、反発することも多くなるでしょう。
特に女の子は、家族よりも友だちとの関係や、やり取りが中心になってきます。
まわりの友だちとの人間関係に対してかなり敏感になると言われています。
友だち・進学・異性関係など、思春期の女の子は多くの悩みを抱えています。
そんなお子さんに、親がしてあげられることは…
・お母さん自身が「何があっても大丈夫!」とドンと安定していること
・子どもの行動を少し距離を取って見守ること
・子どもがSOSを出してきた時は心を込めて聴いていくこと
世話を焼くのではなく「見守る」というスタンスにシフトチェンジしていくのです。
10歳から15歳くらいまでの思春期は、女の子の心が人生で最も不安定になりやすい時期です。
心理カウンセラーをしている方々は、この思春期の時期は、「お母さんはお子さんのそばにいてあげて欲しい」と言っています。
お子さんが苦しい場面に直面した時、いつでもSOSが出せるように、そばにいてあげるということです。
お子さんが学校から帰ってくる時間にはできるだけ家にいてあげるのがベストです。
そこで大切なのは「口を出さずに見守ること」。
「辛い時はいつでも助けになるよ」とおおらかな気持ちでいてあげて下さい。
【まとめ】
女の子は大きくなると、心配事も増えますよね。
親心としてはどうにかしてあげたいと、必要以上に首を突っ込んでしまうことも…
でもそれがかえって問題をより深刻にしてしまうこともあるんですよね。
接し方が難しくなる思春期。
口を出し過ぎず見守り、聞き役に徹してあげて下さい。
小さい時はとにかく溺愛して、少し大きくなったら社会のルールを教え、思春期には見守る。
幸せな女の子に育ててあげてくださいね。

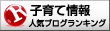


コメント