子育てをする上で、子どもをほめたり叱ったりするのは日常的なことですよね。
それゆえに「自分の接し方は正しいのだろうか……」と不安や悩みは尽きないものです。
ここでは、子どもの心に届くほめ方と叱り方について書いていきたいと思います。
【自尊感情を育む】
自尊感情とは「何ができてもできなくても自分は自分でよい」という存在に対する自信です。
この自尊感情がうまく育っていないと、これからの人生の中でできないことがあった時「こんなこともできない自分には生きている価値がない」と思い詰めてしまいかねません。
また、できていない他人を認めることができず、周囲とぶつかってしまうことがあるかもしれません。
でも、子育てにおいて自尊感情を高めるために大人が、何でも子どもの言いなりになってよいかというとそうではありません。
自分が健康に生きていくために必要な「生活習慣」、人と共存していくために必要な「社会のルール・マナー」を、大人が子どもにきちんと教える必要があります。
これが「しつけ」です。
まず0~3歳時に「自尊感情」を育て、3~6歳時に「しつけ」をしていく。
その先に小学校での勉強がつながっていくのです。
それでは、0~3歳と3~6歳の2段階に分けて、ほめ方・叱り方のポイントをまとめていきたいと思います。
【分かりやすく伝える、0~3歳児のほめ方・叱り方】
うれしい時には感情を共有
0~3歳児の子どもに対しては、言葉と表情や体の動き、声のトーンの変化などを分かりやすく用いることで、大人に受け入れられているという安心感を感じられるようにします。
例えば、ごはんをしっかり食べている時、おむつが濡れていることを知らせてくれた時に、「しっかり食べられたね」「おむつが濡れていたのを知らせてくれたんだね」と言葉にして伝えていきます。
自分で服を脱ごうとした時も、「自分で脱ごうとしたんだね、えらいね」と言葉と豊かな表情で伝えることが、子どもの「もっと自分でやりたい」という気持ちにつながっていきます。
当たり前をほめる
毎日当たり前にしていることも「今日もがんばっていたね」という気持ちを伝えましょう。
子どもは大人の反応を見ながら、自分の行動がよかったかどうかの判断をするからです。
伝えながら子どもの成長を待つ
この時期は言葉を理解することがまだまだ十分ではありません。
大人は言葉で説明するよりも「気持ち」を伝えるといいと思います。
例えば、ケガにつながりそうなことをしようとしている時、「そんなことをしたら危ないからダメ!」と言うよりも、「イタイイタイよ!」と短く真剣に表情で伝えるようにします。
子どもは2歳ごろになると、何でも自分でやろうと挑戦します。
食事や排泄などは子どもが1人でしようとしても、最初のうちは失敗も多いので、ついつい怒ってしまいたくなりますね。
でも過度に叱りすぎてしまうと、子どもは自分から何もしようとしなくなってしまいます。
できる限り子どもが自分でやろうとしている姿を認めるようにしていきたいものですね。
成長すると自我が芽生え、自己主張が強くなる分、友だちとあそんでいる時に友だちのおもちゃを取ってしまったりすることもあります。
そのような場合、言葉で説明して分からせようとしても難しいことがあります。
例えばそういう時は、友だちのおもちゃを取ったことは悪いことですが、欲しかった気持ちに共感し、「欲しかったんだね」「でもお友だちが使っているから返そうね」と繰り返し根気強く伝えていきましょう。
言葉で伝えながらも、子どもが理解できるまで何度でも付き合っていってあげて下さい。
【子どもに納得させる、3~6歳のほめ方・叱り方】
結果だけでなく過程も認める
大好きな大人にほめられることを1つの価値として考える時期です。
結果だけを見て「すごい」「じょうず」とほめるだけでは納得しません。
努力のプロセスも大切にしましょう。
結果だけでほめると「ほめてもらえない自分には価値がない」と感じてしまいます。
子どもが「うまくできなくてもがんばろう」と思えるように、努力のプロセスを認めます。
3歳児以降は、子どもの言語能力も格段に発達するので、ほめられたポイントが徐々にわかってきます。
どこがどうしてよかったのか、ほめられている内容が分かるように伝えてあげて下さい。
例えば「工夫して~したところがよかったよ」など具体的に伝えるといいですね。
単純な言葉だけでのほめ過ぎには注意しましょう。
具体的な言葉で「なぜ」を説明する
3歳を過ぎると、やってはいけないことが徐々に分かり始めてきます。
具体的な言葉で、ゆっくりはっきりと、その場ですぐに伝えましょう。
4歳ごろには他人の気持ちが推測できるようになってきますし、規則やルールのりかいも進みます。
友だちに悪口を言ってしまった時、「自分が言われたらどんな気持ちになるか…」と子どもに考えさせましょう。
叱られた理由が分かることで子どもも納得します。
5歳ごろになると、物事の因果関係が分かり始めるとともに、自分の欲求をコントロールできるようになります。
そのため、欲求を抑えて葛藤することもあります。
そんな時は「このことだけはどうしても許せないって思ったんだね、だから大きな声で言ってしまったんだね」と行為の裏にある気持ちに共感を示してあげて下さい。
叱り方にはユーモアをプラス
大人の言葉で子どもは大変傷ついてしまうことがあります。
叱るつもりが、言葉の選び方によっては全く意図が伝わらないこともあります。
強く叱るだけでなく、叱る時にユーモアを混ぜることも効果的です。
例えば、子どもが自分のぬいぐるみを投げた時、大人がぬいぐるみに対して「痛かったね、あなたは○○ちゃんのことが大好きなのにね…」というように話すと、子どもも我に返ってぬいぐるみに謝ったりします。
「投げるなんて悪い子!」と子どもの人格を否定するのではなく、「腹が立ったのはわかるけど、投げるのはよくないよ」と行為そのものについて言うようにしましょう。
「そんな子は嫌い!」「もう知らない!」などの伝え方をしてしまうと、子どもは見捨てられたように感じ、大人を味方と感じなくなってしまいます。
子育ては大変なことも多いですが、大人は子どもにとって「1番の味方だよ」ということが伝わるようにしてあげて下さいね。
\当サイトで使用しているテーマです/
書きやすい!初心者でもデザイン性抜群のサイトに
一番おすすめのWordPressテーマ「SWELL」
【子どもを叱る時に気をつけること】
◇マイナスの言葉で叱らない◇
子どもを叱る時、ついつい「なんでそんなことするの!?」「早くしなさい!」なんて声をかけてしまうことってありますよね。
カウンセラーの波多野ミキ先生はこう言っています。
『マイナスの言葉で叱らない』ということです。
【子どもを伸ばす叱り方】
子どもができなかった時、その中でも子どものいい所を見つけて、そこを励ましてあげるといいそうです。
親にほめられた子どもは、自分が認められたと感じ、その良い所を伸ばそうとします。
良い所が伸びれば、それまで欠点だった所が目立たなくなるということです。
もし欠点ばかりをマイナスな言葉で指摘し続けていると、子どもは自分のマイナスな面だけを意識してしまって、実際にそういう姿になっていってしまうそうです。
同じ『少ししかできないこと』に対して「そんなこともできないの?」と言うのと、「もうちょっとでできるね」と言うのとでは、受け取る方も全然違います。
例えばテストで60点とった時「60点しかとれなかったの?」と言われるのと、「60点もとれたの!」と言われるのとではどちらがいいですか?・・・聞くまでもないですよね。
同じ60点でもここまで印象が違うんです。
だから少ししかできなくても、できない方を見て叱るのではなく、できた方に注目してあげる、少しでもできた所やいい所を見つけてあげることで、子どもも自信が持てるようになるそうです。
【本当に叱るときは?】
それではどんな時に本気で叱るのか?
- 自分や人に危険が及ぶようなことをした時(大怪我や命に関わること)
- 反社会的なことをした時(万引きなど)
- 言葉で人を傷つけるようなことを言った時(人の身体的なことをからかうなど)
このような時は厳しく𠮟らないといけません。
厳しく𠮟るといっても、怒鳴ったり叩いたりすることが厳しく叱るということではありません。
しっかり目を見て、静かに真面目に「いけない」ということを言って聞かせることです。
また、先ほども書きましたが、叱る時はいけなかった「行為」をしかるのであって、子どもの「性格や人格」を叱らないようにしてあげて下さい。
例えば、片づけをしない子に対して「片づけをしないでだらしのない子ね、そういう子は嫌いよ」というような叱り方をすると、「自分はだらしないんだ」「お母さんは私のこと嫌いなんだ」と思ってしまうのです。
【まとめ】
ほめる時はその子のいい所を伝えてあげて下さい。「勉強ができる・できない」という評価ではなく、絵を細かく描くのが得意とか、車や電車のことを何でも知っているとか、お年寄りに優しいとか・・・。
子どもは得意なことや熱中していることをほめてもらえると、さらに自信を持つことができます。
そして、その自信が他のことへの興味へと広がっていくのです。
自信がつくと苦手だったことにもチャレンジするようになるかもしれません。
ほめる時には良かった所を具体的に伝えたり、やっている過程や意欲を認めてあげて下さい。
その上でどうすればうまくいくか一緒に考えてあげることが大切です。
それが、物事に積極的に取り組める姿勢を育てていくことになると思います。

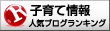


コメント