子どもは大人に比べて抵抗力が弱く、ちょっとした気温の変化などの影響で、鼻水の症状があらわれます。
大抵の鼻水は風邪の場合が多いのですが、いつまでも治らない鼻水は他の病気を引き起こしている可能性も考えられます。
「鼻水くらい大丈夫」と放っておくと、思わぬ病気になったり重症化したりすることも少なくありません。
そうなってしまう前に、早めに対処をしてあげましょう。
【鼻水が与える赤ちゃんへの影響】
子どもの鼻の特徴
子どもの鼻の中は狭く、鼻と耳をつなぐ耳管が太く水平のため、ウイルスが入りやすい構造になっています。また、子どもの鼻はちょっとした環境の変化で鼻水の分泌が増えやすいのも特徴です。
鼻水が詰まるとどうなるの?
中耳炎になってしまうことがあります。鼻と耳は耳管という管でつながっています。ウィルスや細菌を含んだ粘り気のある鼻水が耳管へ流れ込み中耳に入ると、炎症を起こし中耳炎になってしまうことがあります。
また息苦しくなり、ミルクが飲めなくなったり、夜眠れなくなる。 その結果、体力の低下を引き起こし、風邪が長引くなど、赤ちゃんに様々な悪影響を及ぼします。
【鼻水が引き起こす代表的な病気】
中耳炎
鼻水に含まれる細菌やウイルスが耳と鼻をつなぐ耳管を通じて耳に入り込み、中耳炎を引き起こしてしまうことが多くあります。
子どもの耳管は大人に比べて太くて水平で、細菌やウイルスが鼻から耳へ入り込みやすい構造になっています。
そのため中耳炎になりやすく、注意が必要です。
耳を痛がる、発熱、耳だれが出る、聞こえにくさなどの症状があれば中耳炎かもしれません。
放っておくと重症化したり難聴になったりするおそれもあるので、すみやかに耳鼻科を受診しましょう。
副鼻腔炎
鼻の穴は鼻腔とよばれますが、さらに奥にある顔の中の空洞部分を副鼻腔とよびます。
その副鼻腔に細菌やウイルスが侵入し、炎症を起こした病気が副鼻腔炎です。
色の濃い粘ついた鼻水が出る、鼻づまり、頭痛、顔の痛みなどがおもな症状です。
3ヶ月以上続くと慢性副鼻腔炎とよばれ、症状が長期化、慢性化してしまうことも多くあります。
慢性化すると治りにくくなるため、できるだけ早く治療を開始し、完治するまで根気強く通院することが大切です。
【鼻水は吸引することが大切】
赤ちゃんは自分で鼻をかむことができないため、大人が吸引機などで吸ってあげる必要があります。
市販の吸引機もいろいろありますが、スポイド式は吸引力が弱く、鼻の出口付近に出ている鼻水を取り除く程度のものがほとんどです。
一方で、大型電動式は、病院で行う鼻吸い器で強力なタイプです。鼻はよく取れますが、強く吸いすぎることで、鼻粘膜や鼓膜に影響が出る場合もありますので、家庭での使用の際は注意が要ります。
ご家庭での使用でおすすめは、小型電動式か口吸い式です。特に小型電動式は、楽に吸引できる点でもおすすめです。

【吸引の他お家でできる鼻水ケア】
- 部屋を加湿する…乾燥を防ぐことで鼻の通りが良くなり、呼吸がラクになります。
- 鼻をかむ…鼻をすすらないように片方ずつ小刻みにゆっくりとかませてください。このとき、強くかみすぎないように注意しましょう。
- 部屋の湿度を高め、綿棒やガーゼなどでやさしく拭き取る…鼻の粘膜を傷つけないように、やさしく詰まった鼻水を取り除きましょう。
- 蒸しタオルや吸入器を使う…鼻に蒸しタオルを当てたり、吸入器で蒸気を吸わせると、粘度の高い鼻水も取れやすくなります。またお風呂の後や、温かい物を食べた後なども鼻水が取れやすいです。
【鼻のかみ方の練習法】
大きくなったら自分で鼻をかむ練習をしましょう。
①口を閉じて鼻から「フン」と息を吐く。ティッシュを鼻の前に下げておくと、息が鼻から出ている事がわかりやすくなります。
②鼻の穴の入り口に手をあて、鼻から「フン」と息を出して、空気がでてくるのを自分の手で実感させます。
③鼻の穴の一方を押さえてかむようにする。鼻水が飛び散って汚いと思う方は、お風呂場で練習することをオススメします。お風呂の蒸気で鼻も通りやすくなって一石二鳥ですよ。
鼻かみ練習の始めどき
個人差はありますが、3〜4才くらいになったら鼻のかみ方を教える時期です。
ポイントは、片方ずつかむこと。
片方の鼻をきちんと押さえて、鼻をかむ前には、口から大きく息を吸う。
そしてゆっくり少しずつかむ。
両方一度にかませたり、力いっぱいかませたりすると、耳を痛めることがあります。
あわてず、ゆっくり、少しずつかみ残さないように心がけてあげましょう。
【まとめ】
いつまでも止まらない子どもの鼻水を放っておくと、風邪や感染症のリスクも高くなります。
たかが鼻水と思わず、いつまでも治らなかったり、色が濃くて粘っこい鼻水が出たりする場合は早めに耳鼻科を受診することをオススメします。

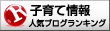

コメント